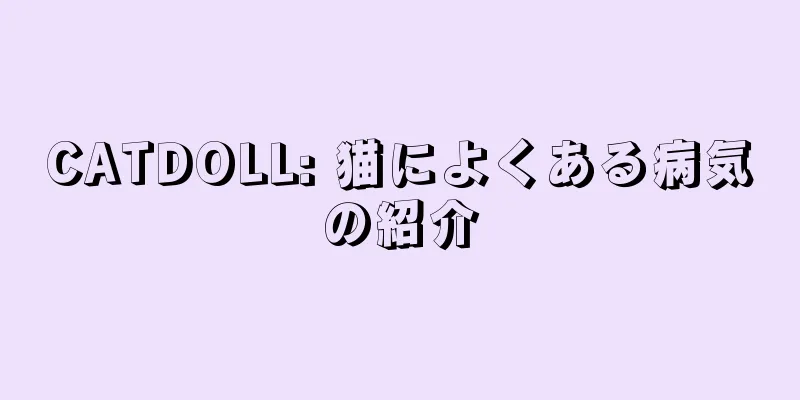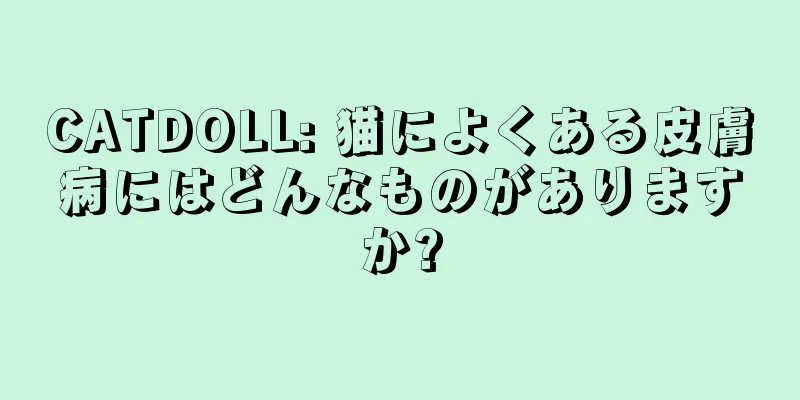1. 交差ウイルス感染
原因と症状
この病気は、病気の猫との接触やインフルエンザ菌の感染によって引き起こされます。症状は流行しているウイルスによって異なります。細菌性鼻気管炎と非常によく似た症状が現れることがあります。肺炎、関節炎、口腔内潰瘍、腸管感染症などを引き起こした場合は、特別な症状は現れません。肺感染症は最も恐ろしいです。丸まる、歩く、呼吸が不安定になるなどの症状が出たら注意しましょう。
【治療とケア】
主な目的は、猫が自力で病気を克服できるように支援することです。そのため、発症後は体温管理と水分・栄養補給に注意してください。また、できるだけ早くワクチン接種を受けてください。
2. 原虫感染
原因と症状
この病気は真菌の感染によって引き起こされます。このカビは乾燥したハトの糞の中に存在し、空気中に浮遊し、皮膚に触れたり吸入したりすると感染を引き起こします。しかし、健康な猫が感染することはほとんどありません。呼吸器官が感染すると、鼻水やくしゃみによって肺炎が起こります。皮膚が感染すると潰瘍や腫瘍などの症状が現れます。目が感染すると失明する可能性があります。
【治療とケア】
正常な免疫力を持つ猫はこの病気にかからないので、まずは異常な免疫力を治さなければなりません。症状は皮膚疾患から始まることが多いため、できるだけ早く発見することが重要です。
3. ノミアレルギー性皮膚炎
原因と症状
ノミが血を吸うと、刺激物質を含む唾液を吐き出し、それが皮膚の奥深くまで浸透してアレルギー反応を引き起こし、この病気の原因となります。かつてはノミによるアレルギーは夏に起こることが多かったのですが、最近では室内暖房設備の普及により、一年中アレルギーが起こる可能性があります。首から背中、腰から尻尾まで、傷や湿疹だらけです。かゆみのある部分を噛んだり引っかいたりすると、脱毛や皮膚の発疹が生じます。
【治療とケア】
ステロイドで治療している間は、猫と家を徹底的にノミから掃除してください。
4. 毛球症
原因と症状
猫はセルフケアを行う際に、胃の中の毛を食べるため、毛玉ができることがあります。この病気は、毛玉が大きすぎて吐き出せなかったり、腸まで届かなかったりすることで起こります。症状としては、食後に頻繁に嘔吐し、嘔吐物に毛玉と食物の両方が含まれることが挙げられます。
【治療とケア】
赤ちゃんが1~2か月に1回吐き、吐いたものの中に毛玉だけが入っている場合は、心配する必要はありません。しかし、あまりにも頻繁に嘔吐する場合は、病院に行って検査を受けるのが最善です。薬を服用している間、飼い主は猫の体に入る毛の量を減らすために、定期的に猫の毛のケアも行う必要があります。
5. 角膜炎
原因と症状
猫同士の喧嘩による角膜損傷、まつ毛の内側の炎症、細菌やウイルスの感染などにより、この病気が発生します。猫が涙を流していたり、寒さを感じていたり、光のまぶしさを感じていたりする場合は、状況を注意深く観察してください。猫は瞬膜が露出したり、角膜が白くなったり、濁って眼球の内部がはっきりと見えなくなることがあります。慢性炎症がひどい場合は、眼球内部にまで広がり、厄介な事態になることがあります。
【治療とケア】
病気が発生すると、角膜の劣化が急速に進むため、発見した場合はすぐに病院に行く必要があります。医師の指導のもと、薬を服用したり点眼薬を使用したりしてください。ただし、人間用の目薬は絶対に使用しないでください。猫が目をこすったり引っかいたりするときは、エリザベスカラーをつけてください。
6. 結膜炎
原因と症状
細菌やウイルスの感染、外傷、アレルギー、薬剤や植物による刺激、ゴミ、ほこりなどが原因で起こります。猫ウイルス性鼻気管炎や猫風邪の細菌感染などの症状があります。目やに、頻繁な瞬き、涙、瞬膜の露出。重症の場合は結膜の腫れを引き起こすこともあります。
【治療とケア】
結膜炎の原因となる病気が重篤な場合は、まず医師の治療を受けてください。目の周りの汚れをきれいにし、病院で点眼薬をもらい、医師の指示に従って猫の目に点眼してください。犬が目を掻く傾向がある場合は、エリザベスカラーを使用してそれを防ぎましょう。
7. 外耳炎
原因と症状
この病気は細菌、真菌、または耳シラミなどの寄生虫によって引き起こされます。この病気は、耳に水が入ったり、不注意に耳かきをすることで怪我をしたりすることでも起こる可能性があります。病気の初期段階では、猫の耳はひどくかゆくなり、猫は頭を振ったり耳を掻いたりし続けます。すぐに、少し黒い耳垢が現れ、不快な臭いがします。鼓膜が破れて水疱や膿疱が出現し、中耳炎に進行します。この時、耳のかゆみはなくなりますが、非常に痛いので、猫は耳を触られるのを嫌がります。
【治療とケア】
外耳炎が治るまでは、お風呂に入れるときに猫の耳に水が入らないように注意してください。猫は耳を触ることを嫌がるため、より正確な診断をするためにはまず麻酔を施す必要があります。
8. 耳の疥癬
原因と症状
耳に寄生する耳ジラミの一種である耳ジラミによって引き起こされる病気。疥癬にかかった猫と接触すると感染する可能性があり、猫が小さいほど感染の可能性が高くなります。頭、首、腹部、足の先、耳がひどくかゆいです。猫は一瞬も休むことができず、あちこちをこすったり引っかいたりし続けます。耳に症状が現れると、黒い耳垢が出たり、耳が激しく震えたりします。この病気は皮膚炎、脱毛、さらには外耳炎を引き起こす可能性があります。
【治療とケア】
病院に行って、皮膚に寄生虫がいるかどうか調べてもらいましょう。見つかった場合は薬を服用するか、薬浴をしてください。引っかき傷や抜け毛を防ぐためにエリザベスカラーを着用してください。
9. 感染性貧血
原因と症状
この病気の別名は猫伝染性貧血症です。病原体であるネコ伝染性貧血菌は赤血球に寄生し、赤血球を破壊して貧血を引き起こします。症状には、鼻先や歯茎の青白さ、息切れ、運動時の失神などがあります。ノミなどの吸血昆虫は病気の媒介となる可能性があります。
【治療とケア】
貧血は抗生物質で病原菌を殺すことで治ります。ただし、免疫力が弱まっている場合は治療効果が明らかでない場合があります。まず、猫の体力を高めるために、栄養バランスの取れた食事を与える必要があります。
10.便秘になる
原因と症状
便秘は病気ではありませんが、他の病気を引き起こす可能性があるので注意が必要です。脊椎の異常により神経が圧迫され、大腸が拡張して排泄ができなくなることがあります。肛門付近の化膿や膿瘍により排便が困難になることがあります。トイレが汚れすぎたり、精神的なストレスがあったりすると、便秘になることもあります。症状としては、排便時と同様の姿勢で数日連続してトイレに座っているが、排便ができず、無気力になり、食欲がないなどが挙げられます。
【治療とケア】
軽い便秘は、食べ物にバターやマーガリンを少し加えるだけで治ります。重症の場合は浣腸が必要になります。浣腸後、液体以外の便が出ない場合は、便を除去する手術が必要となります。
11. 歯周炎
原因と症状
歯をきれいにしないと、すぐに歯垢が形成され、歯に付着してしまいます。柔らかい食べ物ばかり食べ続けることも歯石ができる原因の一つです。歯石が形成されると、すぐに歯の周囲に炎症を引き起こし、それが歯痛、歯肉炎、歯根炎、歯茎の緩みや腫れ、口臭に発展し、最終的には歯がぐらぐらしたり抜け落ちたりすることになります。
【治療とケア】
柔らかい缶詰の食べ物に加えて、乾燥した食べ物や干し魚などの硬いものも猫に与えてください。定期的に猫の獣医に歯石の除去を依頼し、治った後は柔らかい食べ物を与えてください。
12. 髪のもつれ
原因と症状
尾の付け根にある皮脂腺が活発に活動し、分泌物で尾が汚れてベタベタになります。重症の場合は分泌物が蓄積して塊を形成し、すぐに脱毛が始まります。細菌感染後には出血や化膿が起こることもあります。この病気は、去勢されていないオスの猫、特にペルシャ猫やチンチラ猫などの長毛種によく見られます。
【治療とケア】
基本的な方法はシャンプーで分泌物を洗浄することです。病気が慢性化すると外科的治療が必要となり、猫が患部を舐めないようにエリザベスカラーが使用されます。最も効果的な予防方法は去勢です。
13. 白血病ウイルス感染
原因と症状
この菌は血液を介して感染しますが、菌の強さは比較的弱いため、毎日病気の猫と接触したり、喧嘩などで感染したりしない限りは心配する必要はありません。感染すると白血病や胸部の悪性腫瘍を引き起こす可能性があります。免疫力が低下するため、他の病気に非常にかかりやすく、怪我をすると回復が困難になり、鼻水が絶えず出たり、口腔内に炎症が起こったり、体重が減少したり、鼻先や唇、舌に白い苔がついたりします。
【治療とケア】
現在、この病気に対するワクチンや治療法はありません。しかし、症状に応じて適切な処置を行えば、症状の悪化を防ぐことができます。主な予防方法は、病気の猫との接触を避けることです。
14. ウイルス性気管炎
原因と症状
この病気は一般に猫風邪として知られています。この病気は、感染した猫のくしゃみや鼻水に含まれる単純ヘルペスウイルス(HMS)菌によって引き起こされます。感染後4~5日で、猫は突然、無気力、発熱、食欲不振、継続的なくしゃみや咳などの症状を発症します。猫によってはよだれを垂らしたり、涙を流したり、結膜炎に悩まされたりすることもあります。この病気は通常2週間で回復しますが、抵抗力が低下した状態で他のウイルス感染を引き起こすと、治癒に長い時間がかかります。
【治療とケア】
分泌物で汚れた目と鼻を洗うために病院へ行ってください。暖かくして安静にし、水分と栄養を補給し、細菌感染を予防してください。この病気はワクチン接種によって予防および治療することもできます。
15. 感染性腸炎
原因と症状
この病気は、病気の猫の糞便、大便、唾液、嘔吐物中に排出される猫伝染性腸炎菌によって引き起こされます。この細菌は非常に蔓延しており、腸炎を引き起こすだけでなく、猫の他の病原体に対する抵抗力を弱める可能性もあります。症状は激しい嘔吐、持続的な高熱、そしてほとんど食欲がない状態から始まります。子猫が感染すると、徐々に下痢や血便が出始めます。 3〜4日以内に致命的になる可能性があります。妊娠中の猫がこの病気にかかると、流産や死産につながる可能性が高くなります。ですから、この病気は非常に恐ろしいのです。
【治療とケア】
水分と栄養を補給し、猫自身の力に頼って病気を克服する方が、薬よりも効果的です。これを予防する最善の方法は、猫が若いときにワクチン接種を行うことです。
16. 感染性腹膜炎
原因と症状
この病気は、病気の猫のくしゃみや尿の中に潜む猫伝染性髄膜炎菌の感染によって引き起こされます。母猫が細菌の保菌者であれば、産道を通じて赤ちゃんにも感染する可能性があります。感染すると、腹部と胸腔内に体液が蓄積し、腹部に腫瘍が発生します。胸水は肺を圧迫して呼吸困難を引き起こし、また、精神的抑うつ、食欲不振、発熱、下痢などの全身症状を引き起こすこともあります。貧血や神経症状が現れると、病状が悪化していることを示します。
【治療とケア】
効果的なワクチンがないため、症状の緩和に重点を置いた治療しか選択肢がありません。根気強くやり続けてください。
17. 免疫不全ウイルス感染症
原因と症状
猫同士が噛み合うと、細菌は保有者の唾液を通じて広がるため、外に出ない猫は病気に感染しません。感染後約1年で、軽い下痢、リンパ節腫脹、細菌感染などの症状が再発します。数年後には慢性口内炎、慢性口腔内潰瘍、目やに、鼻水、発熱、下痢などの症状が現れます。病気の末期にはエイズ(後天性免疫不全症候群)を発症し、身体が急速に衰弱します。
【治療とケア】
この病気に対するワクチンはありませんが、エイズを発症する前に正しい治療を受ければ、すぐに命に関わることはありません。家庭でゆったりとした給餌方法を採用することで、寿命を延ばすこともできます。
18. 口内炎
原因と症状
この病気の一般的な原因は、免疫力の低下と感染症による口内炎です。また、細菌、真菌、歯垢の付着、ビタミン欠乏などもこの病気を引き起こす可能性があります。この病気が発生すると、口臭、よだれ(多くの友人から「猫がよだれを垂らしているが、これは病気だ!」と言われました)、食事中に痛みを感じるなどの症状が現れます。口を開けたときに歯茎が潰瘍化し、腫れ、出血している場合は、口内炎になっている可能性があります。
【治療とケア】
口を清潔にし、抗生物質を使用して細菌の増殖を抑制し、薬を使用して炎症の進行を抑制します。口腔粘膜を刺激する可能性のある大きくて硬い食べ物を避け、代わりに小さくて柔らかい食べ物を食べるようにしてください。毎日猫の歯を磨き、定期的に歯石を除去することも予防の役割を果たします。